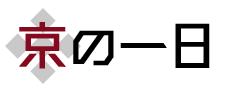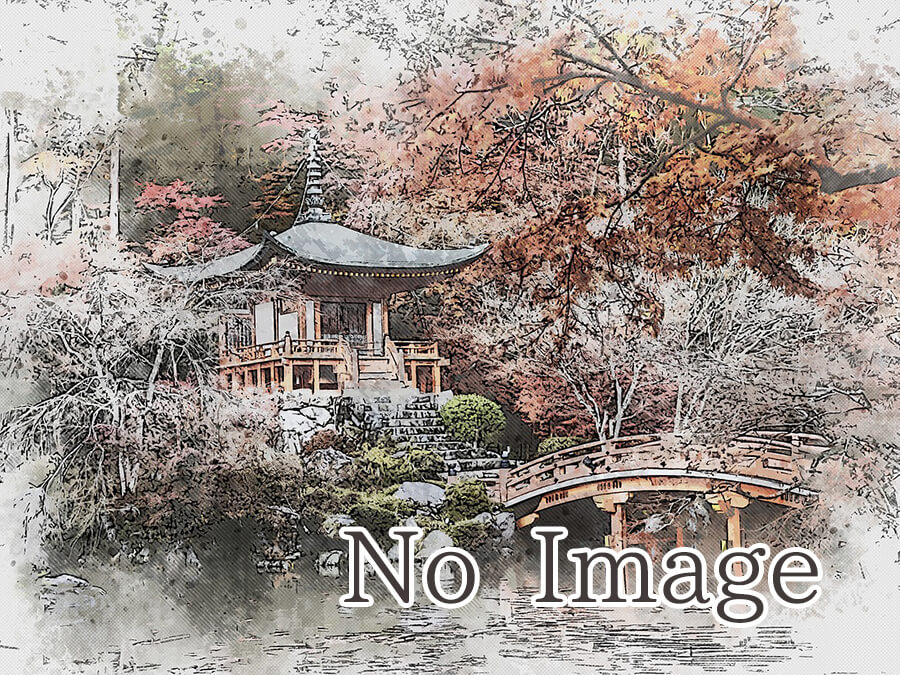
本能寺の変で有名なお寺
鴨川のほとりに法華宗の法灯を長年掲げ続けている、本能寺。
織田信長と明智光秀の戦いで名前を知っている人も多いのではないでしょうか?
第一の設立は1415年、日隆聖人が、油小路高辻と五条坊門のちょうど間の土地を使って建築したことで知られていますが、その三年後に、破却。
その後、再建と破却、焼失などが繰り返され、現在の設立されている本能寺は実に第七の設立になります。
設立されたのは1928年ですので、実は意外と最近なのです。
織田信長公の巻き込まれた本能寺の変は、1582年の、第四の設立の際の本能寺。
その前後に、幾多も焼失があることを知ると、ちょっと驚きですよね。
織田信長と関係が深い
冒頭でもお話ししましたが、本能寺と織田信長は、切っても切れない関係といえるほど、織田信長にとって非常に馴染みが深い場所として知られています。
決してあの有名は本能寺の変の時のみではなく、実は織田信長は、記録にあるだけでも4回は、本能寺に滞在していたのです。
本能寺に滞在していた理由は、決して静養が目的ではありません。
天皇家と近づくために、本能寺に滞在して仏教の教えを請い、天皇家とのつながりを持とうと画策したり、鉄砲や火薬の交易の手助けをさせるために滞在場所として利用したりなど、何かと理由があったうえで本能寺を利用していたのではないかといわれています。
本能寺の変の前の本能寺は、現在の本能寺に比べると非常に大きく、広い作りになっていたと同時に、高い塀、深い堀に囲まれていたため、安全面も非常に強固であったといわれていますので、安全に過ごすことが出来る場所として、何度も滞在をしていたという説もあるようです。
本能寺の毎朝のお勤め
本能寺では、境内本堂にて、毎日朝のお勤めがされています。
参拝は自由に行うことが出来る上に、本堂には椅子席が用意されているため、日々参拝をされているという方も少なくないようです。
時間は毎朝六時からですので、ご年配の方を中心に、信心深い信者の方なども、広く利用をされているといわれています。
また毎日の産廃のほかにも、季節に応じた様々な行事が行われています。
一月は元旦祝祷絵という、一年の国の安泰や、身体安全、家内安全などの祈願を行う行事が主流です。
参拝客も非常に多く、この行事に参加をするために、遠方から参拝に訪れるという方も少なくありません。
また、海外からも織田信長ファンが訪れることが多いのが本能寺の特徴で、参拝をすると同時に、信長の最後の地を見に来たという方も多く、観光スポットとしても知られています。
このように、織田信長と切っても切れないような関係を持っているのが、本能寺の最大の特徴であるといえるでしょう。