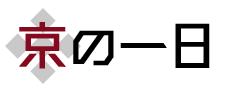国内だけでなく、世界中から観光客が集まる日本の古都・京都。古い街並みや歴史ある建造物が立ち並び、国指定の重要文化財は約300点と、全国一の数を誇っています。
このページでは、京都に行くなら絶対に押さえておきたい定番観光地の中から、特に映えやすいスポットに着目しておすすめのポイントをまとめました。
「映える」写真の撮り方のコツや上手についてもお伝えしています。
まだ京都へ行ったことのない方もリピーターも、ぜひこちらをチェックしてスマホ片手に京都めぐりへ出かけてみてください。
伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)
「お稲荷さん」として親しまれる伏見稲荷大社は、全国に約3万社もあるとされる稲荷神社の総本宮です。
その歴史は1300年以上と平安遷都よりも古く、商売繁盛や家内安全のご利益があるとされ、季節を問わず多くの参拝者が訪れます。
伏見稲荷大社と言えば、鮮やかな朱塗りが美しい「千本鳥居」が有名。
アニメやゲームの世界に迷い込んだ異世界感と幻想的な雰囲気は海外の観光客にも人気で、絶好の映えスポットとなっています。
明るい時間帯の撮影でも十分きれいですが、せっかく撮影するならライトアップが行われる「講員大祭」のシーズンがおすすめ。
10月1日~10日までと期間は短いですが、18時からはじまる「千本灯籠」と呼ばれるライトアップは、いっそう神秘的な一枚に仕上がります。観光のタイミングが合う方は、ぜひライトアップ期間に参拝してみてはいかがでしょうか。
賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)
鴨川の下流にあることから、「下鴨神社(しもがもじんじゃ)」とも呼ばれる賀茂御祖神社。日本で5番目に登録された世界文化遺産として知られています。その歴史は非常に古く、奈良時代よりも前から存在していた記録があるほど。勝利、厄除、縁結び、子宝・安産、子育て、交通安全など、多くのご利益があるとして一年を通して賑わっています。
下賀茂神社の摂社として祀られている神様「玉依姫命(たまよりひめのみこと)」は女性で、それは玉のように美しかったそう。そのため、美麗の神としての信仰が深く、美しくなりたいと願う女性に人気のパワースポットでもあります。
コスメでメイクアップされた手鏡の形の絵馬が奉納されているスペースは、可愛い上に映えること間違いなし。
絵馬の奉納後は境内で「美人の水」をいただける、美しくなりたいと願う女性にぴったりのスポットです。
また、賀茂御祖神社には干支を守る神様「大國さん」も祀られています。立ち寄った際には、ぜひ自分の干支を参拝してさらにご利益をいただきましょう。
南禅寺(なんぜんじ)
南禅寺は、今から730年以上も前の1291年に開創された、臨済宗南禅寺派の総本山。
境内全体が国の史跡に指定されていて、国宝「方丈」や「三門」などの重要文化財に指定されたスポットが複数あり、見どころ豊富なお寺です。
特に三門は、石川五右衛門の「絶景かな、絶景かな。」という言葉でも知られるほど。
紅葉シーズンになると赤々とした紅葉が広がり、情緒あふれる景色を楽しめます。
訪れたら必ずカメラに収めておきたい、まさに絶景です。
おすすめの映えスポットは、それだけではありません。南禅寺のレンガ造りの水路閣は、人気のフォトスポットとして多くの人が訪れます。サスペンスドラマなどでもロケ地でよく起用される場所なので、一緒に行った人と一緒にサスペンス風の撮影を楽しむのも良いですね。
少しでも思い出に残る写真を写そうと、着物姿で訪れる方も多いポイントです。
渡月橋(とげつきょう)
嵐山の前を流れる大堰川に架かる渡月橋は、言わずと知れた嵐山のシンボル。春には桜、秋には紅葉の名所として有名で、毎年多くの人が訪れる京都の王道スポットです。
長さ155m、幅11mの木製で、月が橋を渡るように動いていく様から名づけられました。
バックの嵐山とのコンビネーションは絶景。
どのシーズンに訪れても四季の美しさを楽しめますが、桜や紅葉のシーズンになると大勢の観光客が押し寄せ、人や車で混雑するほどです。
遠目からの橋の写真や橋を渡る様子を撮るのも良いですが、せっかくなら船で大堰川を巡りながら贅沢に絶景を味わいましょう。
船頭さんが竿一本で遊覧する屋形船や自由に漕げるボートなど、さまざまな船で観光できるようになっています。
夏には鵜飼ツアーもあり、かがり火の中で鵜飼見物を楽しめます。ふだんではなかなか経験できない日本の風物詩を存分に楽しみながら、屋形船で料理に舌鼓を打つのも贅沢なひとときです。
屋形船での遊覧や鵜飼ツアーは、事前に予約しておくことをおすすめします。
竹林の小径(ちくりんのこみち)
渡月橋の北側にあるのが、美しい竹林の道が続く「竹林の小径」です。渡月橋と並んで嵐山の人気観光スポットとして知られています。
しっかりと手入れされた約400mの竹林は壮観で、はるか昔の山の中にタイムスリップしたような雰囲気を楽しめます。
実際にこのエリアは、平安時代には貴族の別荘地だったといわれており、すがすがしく心地良い風景。晴れた日には、木漏れ日の光に癒されること間違いありません。紅葉の季節にはもっとも美しい竹の様子が見られるほか、冬には竹林の両側がライトアップされる「嵐山花灯路」が開催されます。
なかなか見ることのできない幻想的な夜の竹林をカメラに収めたい方は、冬のシーズンに訪れるのがおすすめです。
「竹林の小径」の人気のめぐり方は、伝統的な人力車に乗車しての観光。リクエストすれば行きたいところに立ち寄ってくれるほか、知る人ぞ知る路地裏などのルートも案内してくれます。
貴船神社(きふねじんじゃ)
京都を流れる鴨川の水源地に位置し、京都の「水源を守る神様」として信仰される貴船神社。
古くは「氣生根(きふね)」と表記されていたこともあり、万物のエネルギーである「氣」が発生する地として大切にされてきました。
根本の地参拝時に利用する「絵馬」の発祥地といわれるほか、縁結びのパワースポットとしても知られています。
京都の貴船神社の歴史は古く、少なくとも1300年以上前から信仰されていた記録があるそう。日本にある約450社の貴船神社の総本山でもあります。
夏は京都の市街地よりもひんやりとしているため、避暑を目的に訪れる方も多いとのこと。
美しい石段の両脇に続く色鮮やかな朱色の灯籠は、必ずスマホに収めておきたいところです。
また、貴船神社では全国的にも珍しい水占みくじ「「水占斎庭(みずうらゆにわ)」」を引くことができます。
占いの用紙を水に浮かべると数秒ほどで文字が浮き上がってくる仕組みで、恋愛や仕事、旅行、出会い」など、気になる未来を占ってみたい方におすすめです。
三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)
三十三間堂は、千手観音を祀る寺院として知られる本堂の通称で、正式名称は「蓮華王院(れんげおういん)」と言います。
三十三という字は、南北にのびる内陣の柱間が33もある特徴に由来しています。これは、観音菩薩の変化身「三十三身」にも基づく数字です。堂内の壇上には、黄金の観音様の像1,000体が並べられています。そのほか、千手観音坐像や千体千手観音立像、風神・雷神像など多くの国宝が見られる寺院でもあり、観光地として大人気となっています。
お堂のなかは撮影禁止なので千手観音像を撮ることはできませんが、三十三間堂の見どころでもある「通し矢」が行われた歴史のある120mの長い本堂は圧巻です。
また、三十三間堂にちなんだ3月3日には、「春桃会(しゅんとうかい)」と称して、華道・池坊流による献花式と花展が開かれます。拝観通路上には特別な高壇が設置され、いつもとは違った雰囲気の本堂を楽しめるほか、女性限定のお守り授与も行っているので、せっかくならスケジュールを合わせて訪れるのも良いかもしれません。
スマホで「映える」写真を撮るコツ
せっかく京都へ観光に訪れたのですから、少しでも良い写真を残したいものですよね。映える写真の撮影に成功したら、すぐにでもSNSへアップしたいものです。
スマホのカメラで「映える」写真を撮りたいなら、以下のようなポイントを押さえるのがおすすめです。
ここからは、スマホで映える写真を撮るコツやポイントを紹介していきます。
構図を考える
写真を撮る際、構図を意識するだけでも簡単に「映える」雰囲気を作り出すことができます。単に正面から全体を撮るのではなく、見せたいものがより伝わりやすいよう構図を意識しましょう。
真上からの構図は食べ物を撮るときなどによく使われますが、風景や景色であれば、三分割した線上に被写体を置くのもおすすめです。スマホに搭載されているグリッド機能を使用すると、画面上に三分割線が表示されるので、撮影しやすくなります。
アングルを変えてみる
同じ被写体でもアングルを変えるだけで、映える写真になりやすくなります。観光地での建造物や風景を写すなら、まっすぐに構える水平アングルだけでなく、上から見下ろすハイアングルや低い位置から見上げるローアングルなど、さまざまな角度から写してみましょう。SNSなどで、おしゃれだと思う写真のアングルを真似してみるのもおすすめです。
自然光で撮影する
シャッターを切るとき、フラッシュなどを使わずに自然の光で撮影すると、目で見たままを表現できるのでキレイな映える仕上がりになりやすくなります。
室内の撮影でも、太陽光が当たる場所に移動するなどフラッシュを使わずに撮影する工夫をしてみましょう。
被写体に対し斜め前や横から光があたるように調整すると、より仕上がりがキレイになります。
ズーム機能を使わない
映える写真を意識したいなら、スマホのズーム昨日は使わないようにして撮るのがおすすめです。近くで撮りたい場合は、自分自身が被写体に近づいて撮影するようにしましょう。
なぜなら、スマホで採用されている「デジタルズーム」を使って撮影すると、拡大するほど解像度が低くなってしまい、荒い仕上がりになってしまうからです。どうしてもズーム写真を撮りたいのであれば、スマホの「アナログズーム機能」を使うようにしてください。